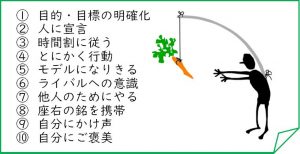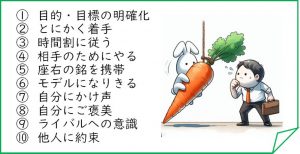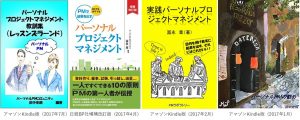表題
『超高齢社会の下準備(ある日妻の介護が必要になりました)』
副題
『介護とは いずれ我が身 もうすぐ我が身』
皆様へ,
私たちは,令和5年11月4日に,健康管理士会交流サロン主催のパネルディスカッションにおいて介護の問題に焦点を当てました.杉並区で介護経験が豊富な参加者が集まり,お互いに介護に関する情報交換や,介護予防の啓発活動を推進している杉並介護者応援団の北原理事長による基調講演をお願いしました.さらに,パネラーの中川さんからは介護体験について具体的な事例をお話ししてもらって参加者全員で情報共有しました.
ファシリテータの岩石さんからの発言をご紹介します.
私たちはいま,超高齢社会を迎えており,誰もが介護者または介護を受ける立場になる可能性があります.介護保険を賢く利用することで,助けを求めることができる時代となりました.どれだけ努力しても不満が残ることもありますが,できることを無理せず行うことが,介護の基本です.まず,自分がどう生きるかを考え,介護をどう受けるか,どう提供するかを考えることが大切です.
この機会に,超高齢社会に向けた備えを共に考え,助け合いの精神で支え合いましょう.
なお,詳細については下記URLを参照ください.
レポート参照先⇒「第2回健康管理士会交流サロン活動報告会レポート」
-
最近の投稿
最近のコメント
- 「目的」と 「存在意義」こそ 自信の根 に 冨永章 より
- 「目的」と 「存在意義」こそ 自信の根 に 岡田秀文 より
- 丁寧に やれば楽しめ 結果出る に 冨永章 より
- をちこちや 母と分け合う 笑顔かな に 黒田尚 より
- 金魚から 仕事を楽しむ コツ学ぶ に 冨永 章 より
アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年3月
- 2024年12月
- 2024年9月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年5月
- 2023年1月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2018年7月
- 2017年9月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2016年12月
- 2016年10月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年2月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年9月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
カテゴリー
- 1 目的と手段の連鎖
- 1-2 プログラムマネジメント
- 1-3 プロジェクトマネジメント
- 2 行動の段取り
- 3 リスクの予見と対応
- 3-1 リスクの予見
- 4 内発的動機づけ
- 4-1 心理学的な基礎
- 4-2 内発的動機づけ
- 4-3 自信
- 5 関係者への接し方
- 6 プロフェッショナルとしての強み
- 80 失敗録
- 90 書籍の紹介
- 99 WBSテンプレート集
- A モダンPMの積極的な学習
- B 的確なゴール/目的/戦略の設定
- C 系統的な目標/戦術の設定
- D PMの活用とプロジェクトの計画的実行
- E 教訓の継続的な収集・整理と活用
- F 優先度をつけ選択と・集中
- G 作業リストを更新・維持する習慣
- H 大仕事は分解
- I できるだけ先の日程までの予定を立案
- J 予実の対比、大仕事にはEVMを活用
- K 進行を想像することでリスクを識別
- L リスク対応の実行と発生時対処の立案
- M 動機づけの基礎理論の学習
- N 自分自身の動機づけ策の確立
- O やる気喪失への予防と対応策の工夫
- P 大小を問わず達成の経験を累積
- Q 計画と行動に自信をもつ習慣
- R 関係者の識別と相手の立場の理解
- S 関係者の賛同/好感の獲得
- T 関係者の成功/成長に貢献
- U 個人的成功/成長を相手/他人と共有
- V 努力の集中と最善性の追求
- W 模範的WBSの活用・共有・展開
- X コミュニティをリードし社会へ貢献
- Y 勇気を出して挑戦
- Z 苦境からの立ち直り
- 挑戦とレジリエンス
- 未分類
メタ情報