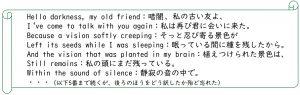個人の孤独なプロジェクトに、多少のことでは諦めず自信を持って取り組み続けるのは余り簡単なことではありませんね。
「歴史的偉人でパーソナルPMに長けた3人を選ぶならば誰か?」とAIに聞くと、即座にベンジャミン・フランクリン、レオンルド・ダヴィンチ、マルクス・アウレリウスの3人という答が返されました。AIへのそれまでのインプットも影響していそうですが、挙げたそれぞれの理由には納得がいきます。そして学ぶべきことが今日でも多いことに気づきます。ここではダヴィンチを採り上げます。
ダヴィンチの優れた創造性と自信に満ちた多くの成果は、必ずしも先天的な能力だけで作られたのではないようです。着想を多数のノートに細かく書きつけ、自分への教訓と行動の拠り所にしていました[1]。この点は「フランクリンの13徳」も同じです。しかしダヴインチが残したノートは数千もあり、集めるだけでも大変な量です。Walter Isaacsonによるダヴィンチの伝記[2]も、全部はカバーしてはいません。逆に要点をカテゴリー別にまとめた書籍は重宝に感じます[3]。
「ダヴィンチのノートで、パーソナルPMに一番重要な知恵を3つ選ぶなら何か?」とAIに聞くと、返ってきた答は次です:
- 問いの力 — 問いこそ未来を切り拓く
- 「問う者は進むべき道を見出す」
- たとえば「なぜ空は青いのか?」「鳥が羽ばたく力は、どこに宿るのか?」
目的と目標の洗練、行動の選択や優先順位づけなどは、自分への問いから始まる。→問いかけによって対象への興味が強まるのも確かだと思います。
- 未完を恐れない — 完璧より前進を
- 「完成よりも、探求の歩みが大事」
- 「未完でも構わない。思索は続くのだから」
完璧を求めて立ち止まるより、僅かずつでも前進を重ねる。それが進化につながり、自信をもった活動ができる。→ダヴィンチの作品に未完が多いのは、それでよいとハッキリ決めたので、自信を失わずに継続できたのかもしれません。
- つなぐ力 — 異物を結びつけると価値の創造ができる
- 「美と機構、音と数、すべてはつなげられる」
- 「美術と解剖学、音楽と数学、・それらは異なるものではない」
異なる経験や別分野の知識をつなぐと、そこには独自の価値が生まれ得る。社会への貢献も、異なるテーマの結び付けから始まる。→今日のイノベーションにも当てはまることです。
この研究会では個人の教訓をLessons Learnedとして抽出し、多くの人にあてはまる知恵の目次として、そのフレームワークを構築してきました。そのような枠組みが個々人の活動の支えになったり、持続的な取組みをする自信につながったりすることを期待しているわけです。
というわけで、パーソナルPM研究会の継続的活動の自信づけにもなることがわかります。ダヴィンチ自身が証明したとも言えそうなノートが、書籍[3]では、「自尊力」「没頭力」「洞察力」「創造力」「実践力」「幸福力」の6つのカテゴリーに分類されており、多くの人に、またこの研究会にもおおいに参考になることを付記させていただきます。
参考書籍
[1]レオナルドダヴインチ著、杉浦明平訳、「レオナルド・ダ・ヴィンチの手記(上/下)」、岩波文庫、1954.
[2] Walter Isaacson, ”Leonardo Da Vinci (English Edition)”, Simon & Schuster, 2017.
[3] 桜川Daヴィんち、「超訳ダ・ヴインチ・ノート」、飛鳥新社、2024.
©2025 Akira Tominaga, All rights reserved.