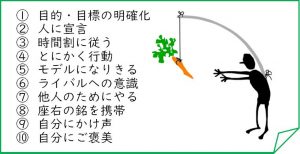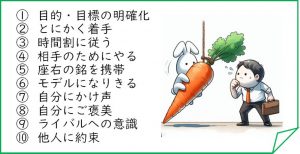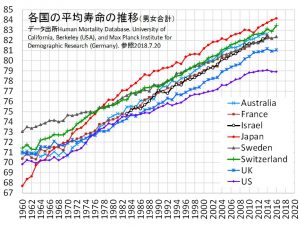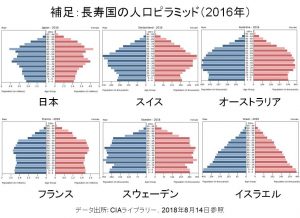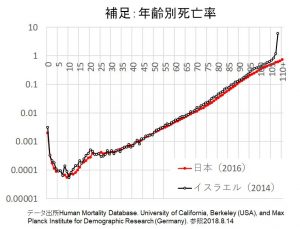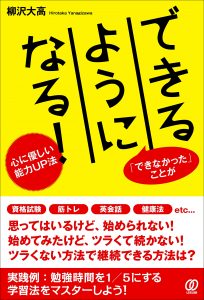「初心忘るべからず」という世阿弥の言葉には、年老いて気づく初心も含まれるそうです。その部類の私には「嫌々やりがちな作業も丁寧にやれば楽しめる」という気づきは、改めて新鮮です。
嫌々やると「へま」をしがちな作業でも、心を込めて丁寧にやればきれいにできるし、作業自体が楽しめます。
最近は好きなマイコン関係の仕事をしていて楽しみながら没頭しがちですが、忙しいと他のことがついぞんざいになり義理を欠いたりします。個人としての優先順位付けが間違っていることにハッと気付き、直す工夫をしていますが、これは別途改めて書くとします。なにせ忙しいですから(笑)。
中学時代の仲のよい友人Hが、酷暑の中、自分の避暑地で採れた新鮮野菜をたくさん持って久しぶりに訪ねて来ました。帰りがけの彼の紙袋にコピーの束が入っているのに気づき、聞いてみると自分の随筆とのことです。時々奥様に見せても興味を示さないので、自分自身が老後に読んで楽しむために溜めているとのことです。ざっと読ませてもらうと他人が読んでも面白そう。彼らしい絵やユーモアが楽しめそうですし、彼の友人多数も登場。思わず「電子本にして出版しよう!」と勧めてしまったのです。
作業日付を都合の良い午後で数回にわけることにしました。そしてその1回目に、「探してみたが電子ファイルはない」とわかり、さあたいへん! しかしこれは彼の「生きた証し」にしようと言いつつ、2人でスキャナーでのOCR変換から始めました。出版まで後3回ぐらいでできると考えました。本人は誤植訂正や校正が多いので結構たいへんでしたが、手伝った私もツールへテキストや絵を入れ込む作業と修正をひたすら行い、中を読む余裕はありませんでした。4週後、4回目の作業でePub完成にこぎつけその場でAmazonの出版処理をして、2人で万歳した後乾杯に出かけました。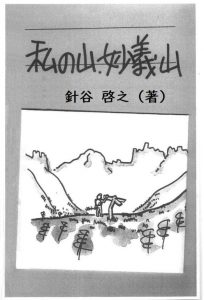
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DGF5RQHQ(サンプルが読める)
さて、私は忙中に単純作業の連続を飽きずにこなせたのは、相手への日頃の感謝だけでなく、上に書いた「丁寧にやれば必ず楽しめる」という法則を時々確認すべくやっていたからにほかなりません。まさにその通りでした。
とはいえ、それだけでは多忙を乗り越えることにはできません。新たな知恵はないかと改めて色々考え試していますが、その気になれば色々あるものです。それらについては回を分けてまた書きます。なにせ読まれる皆様と同じく多忙中ですから(笑)。
©2024 Akira Tominaga, All rights reserved.