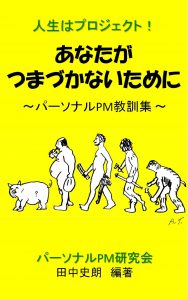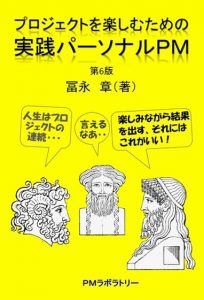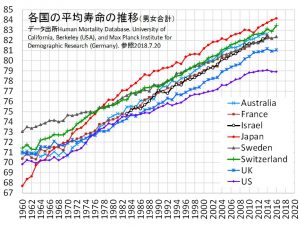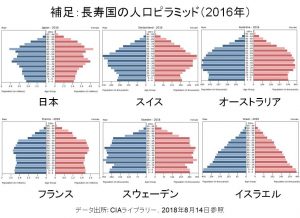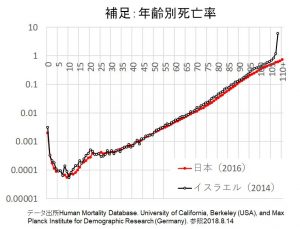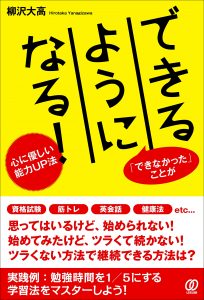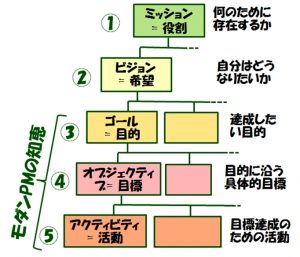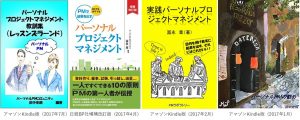「嫌な失敗はさっさと忘れ去る、そのためには思い出さないこと」を長年実践していました。ところが失敗録を書こうということで、ついに思い出してしまいました^^; ある日お客様とのある周年祝賀会がありました。遠い昔のことかと思いましたがなんと僅か4年前、2017年11月のことでした。
午後に大学で講義をした後、時間があったのでいったん帰宅、着替えて出直したのが間違いの元でした。まずいことは重なるもので、電車が珍しく30分も遅延。会場至近の有楽町駅に着いたら開宴時間が間もなくです。改札を出る時に財布を家に忘れたのに気づきました。クレジットカードもそれに入れてあるわけで、「アッ」と思っても後の祭りでした(汗)。
遅刻できませんから会場へタクシーで急ぎたいのですが、小銭入れにも数百円しかありません。「二次会もありそうだしこれはたいへんだ!!」とっさに考えたのは「とにかく会場に着けば知人に借りられるだろう・・・、とりあえずはSUICAにチャージしたばかりだ、1万円ぐらい入ってる!」と。早速窓口へ行くと「SUICA残高から換金はできません!」とのこと。ありゃ、そうか(さらに汗)。
近くにいた駅員さんを捕まえて訳を話すと「お勧めはできませんが、例えば大阪行き乗車券を買って行き先変更すると・・・」??アッそうか!すぐ大阪行き切符を購入し、東京への行先変更をしました。手数料はかかりましたがなんとか現金をゲット。
駅から走ってタクシーをやっと捕まえ、開宴間近の会場へたどり着きました。着いた時は大汗でしたが、無事知人にお金を借りることができました。もちろん翌日の返金振込先もお聞きして。きわどいところをとても助かりました!!
なにせお客様多数のトップが来られ、来賓も多数。記念撮影もあり、特設の二次会もあったのでした。一歩間違えたら大変なことになったなあと考えると、今でもゾッとします。何食わぬ顔で出させていただき楽しみましたが、大いに反省をしたことでした。
それ以来、「移動時間には余裕を十分とる」ように心がけていますし、持ち歩く鞄や小銭入れに札も忍ばせることに。
とはいうものの、このところ外出自粛が長く続いているので、そういう準備の出番がありません。自粛期間が早く明けて欲しいものです。
©2021 Akira Tominaga, All rights reserved.